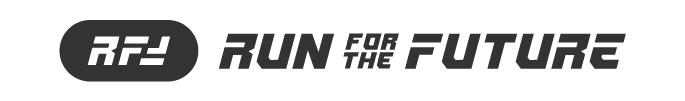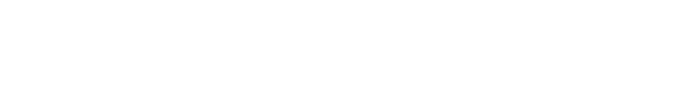こんにちは。
11月もしっかりと駆け抜けました墨田陸上クラブの練習の様子をご覧くださいませ。

4周サーキットアップ
最近は、ウォーミングアップからハードです。1周300mのトラックにて、直線に入る前に補強動作&スプリントドリルを行い、そして直線ダッシュ、カーブはジョギングで繋ぐというサーキットアップを行っています。これを4周するので、走行距離1,200mですね。4周目はヘトヘトになりながらも、最後までやり切るみんなに感激です。

ダッシュ
低学年組は、さらに全身補強運動とダッシュを組み合わせたスプリントトレーニングを行いました。
そして、仕上げのRunメニューは、30m、50m、70m、100m、120m、150mを一本一本集中して取り組んでいきました。最後に、マーカー取りリレーでチーム全員で盛り上がり、良い練習となりました。

300mを行う高学年組
高学年組は、スプリントドリルと補強を行った後、50mと300mのタイムトライアルをメインに取り組んでいきました。先頭についていくもよし、自分のペースでいくのもよし、各々考えながら走ることが大事です。この日は、中学生組も混ざってトレーニングを行いました。高学年と中学生では、明らかな走力差はあるものの、先頭を走る中学生組に行けるところまでついていく高学年も何人か見受けられました。とても大事な事だと思います。勝つ気や挑戦心を持って取り組むことが、技術熟達の一要因となります。その心を大事にしていってほしいと思います。

低学年組の150m(スタート)
さて、本日は、「感覚を捉える」という話をしていきたいと思います。
足を身体の真下に接地することを教わるという場面で、「足で空き缶を潰すイメージ」と言われることがよくあります。確かに、空き缶を潰す際、自分の身体よりも前過ぎても後ろ過ぎても、空き缶は潰しにくいでしょう。力を上手く発揮することができません。
なので、身体の体重を乗せて上手く空き缶を潰すには、空き缶を身体の真下に位置させる、または空き缶を少し手前に置き、乗り込むことで潰すことができます。
これが走りの接地でも同じようで、100%の力を地面に伝えるには、足を前過ぎても後ろ過ぎてもダメで、足を真下に接地する必要があります。これは、作用反作用であり、「科学」です。
これまでの話で、足を身体の真下に接地する意義はある程度理解できたのではないでしょうか。
では、走っている時、「空き缶を潰す」というイメージで走っている人はどのくらいいるでしょうか。空き缶の話を聞きたての人は、「空き缶を潰す」というイメージで走っているかもしれませんが、身近なアスリートである舘野哲也コーチ、谷口耕太郎コーチは、「空き缶を潰す」というイメージで走っているのでしょうか。はたまた、パラアスリートの池田樹生コーチはどのようなイメージで走っているのでしょうか。
おそらく、走る動作としては、身体の真下で接地する動作を行なっているでしょうが、それを各々の特有なイメージ・感覚を持って行なっているのではないでしょうか。この各々のイメージ・感覚を逆転させた時、例えば、舘野コーチのイメージを谷口コーチが持ち、谷口コーチのイメージを舘野コーチが持ち走ってみるとどうなるのか。
両者、互いの感覚をある程度理解はしつつも、真に理解することは不可能であり、他者の感覚を使いこなすことは困難なことのように思えます。
対象物Aは対象物Aでしかないが、対象物Aの捉え方は人それぞれである。今回の話でいえば、足を真下に接地すること(対象物A)は作用反作用という科学的に不変なものですが、足を真下に接地すること(対象物A)を実践する際は、「空き缶を潰す」というイメージ・感覚で表現されたり、舘野コーチ特有のイメージ・感覚があり、谷口コーチと樹生コーチも然り。
人は何かを知る時、他者から教えてもらうことがほとんどだと思います。しかし、それが真を捉えた教えであるかどうかはわかりません。人によりけりです。科学寄りの話なのか、個人のイメージ・感覚寄りの話であるかを見極め、個人のイメージ・感覚寄りの話であれば、そこから科学という根源へと辿る必要があります。
だからこそ、私たちは科学の面を抑えつつ、それを諸個人のイメージ・感覚へと発展させ、実戦で使えるようにする力を養うことが大切なことの一つであると思います。
さぁ、12月も頑張っていきましょう!
(執筆:宮道)
インスタグラムでRFFの日々の練習風景をアップしておりますので、
ぜひご覧ください。
RFFのHPはこちら。
#墨田陸上クラブ#墨田区走り方教室#葛飾区走り方教室#足立区走り方教室#荒川区走り方教室#かけっこ