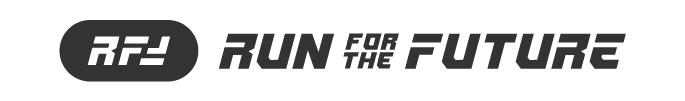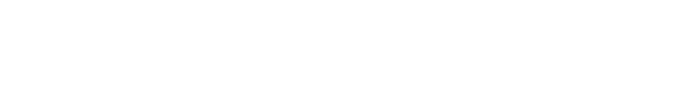こんにちは。
墨田陸上クラブは、夏の川上村合宿を終え、再び墨田フィールドで日々トレーニングを積んでおります。
合宿3日目の様子については近日アップしますので、少々お待ちくださいませ。
それでは、今回の記事では久々の墨田での練習風景をお届けします。
まずはじめに、毎月定例の50m測定会を行いました!ほとんどの人が自己記録を更新しており、夏休み中の練習と合宿での練習の成果がしっかり発揮されていましたね!

片足ジャンプトレーニング
そして、低学年組と高学年組に分かれてメイン練習です。
低学年組は片足ジャンプを中心に練習していき、最後は300mを走りました。

スタートダッシュの練習
高学年組は、スターティングブロックを使ってスタートダッシュの練習です。その後は、ショートダッシュ組と300m組に別れて練習しました。自分が取り組みたい距離の練習を自ら選択する、とても良いことですね。
さて、久々に小話をしたいと思います。
今回は、「速く走る」ということを出発点にあれこれ考えてみます。
陸上競技というものに取り組んで間もない頃には、「こんな練習で足が速くなるのか?」と思うことは少なからずあるかと思います。
始めた当初は、陸上競技の練習とは、「全力で走る」という動作を繰り返すだけかと思いきや、ジャンプ系、ハードル系、投げる系など様々な練習メニューの存在に始めて気づく人もいるのではないでしょうか。
RFF低学年組がよく行う片足ジャンプトレーニングは、走る動作は片足ジャンプの連続であるから、片足で身体を支える力、前に進む力・技術を獲得することに寄与するという意味の下、取り組んでいます。
RFF高学年組がよく行うハードルトレーニングは、より良い股関節の動きを養い、正しい接地と空中で姿勢を保つ体幹などが走る動作に寄与するという意味の下、取り組んでいます。
そして、このトレーニングを経て、これら「走る」以外の動きは、「速く走る」動作を鍛える直接的な役割を持っていたことに気づき、自らの新たな知識として落とし込まれることでしょう。
また、それらの他に、バトンを使ったリレーからマーカー取りリレーなど、競技寄りのものからレクレーション寄りのリレー練習もあります。
では、リレーという練習は「速く走る動作」に対して、どのような寄与があるでしょうか?
リレーでチームを組んで1人100mを走る時と、普通に個人種目のレースのように100mを走る時の違いはなんでしょうか?そこに違いはあるのでしょうか?
リレーの練習は、速く走る練習ではなく、お楽しみ要素が強いもの、ひどく言えば遊びであるという誤解が生まれやすいものであると感じます。
なぜ、そのような誤解がうまれるのか?
これは、リレー練習の意味、なぜリレー練習をするのかという問いの意味が見えづらいからです。
では「意味」を知るにはどうすればいいのか。
それは、意味を模索し続けて意味を知る場合もあるだろうし、答えを知って、そのあとから意味が分かるという場合もあるのではないでしょうか。
意味は1つとは限らないし、「直接的な意味」でわかりやすいもの、「間接的な意味」でわかりにくいものだったりするかもしれません。
そして、多くの人は間接的な意味を軽視あるいは無視するという行為に陥ってしまうという「理解の罠」にハマってしまいます。
たしかに、リレーは、他の練習と比べ「速く走る」ためという意味合いの強さはさほど強くないかもしれない。(これも誤解である可能性はある)
ただ、「速く走る」という動作に間接的に寄与する要素があり、「夢中になって走る」、「楽しく走る」という意味が他の練習と比べて強いと考えられます。この「夢中」と「楽しむ」というものの大切さは不変であると思います。
「見えにくいもの=意味がないこと」という等式は誤った認知であると思います。
あらゆる物事において、意味を考えること、意味の答えを聞いてからまた意味について考えることは、当事者・当事者と関わる者にとって、有意なものになるのではないでしょうか。
陸上競技は色々なことが考えられて面白いですね。
次回の練習も頑張っていきましょー!
(執筆:宮道)
インスタグラムでRFFの日々の練習風景をアップしておりますので、
ぜひご覧ください。
RFFのHPはこちら。
#墨田陸上クラブ#墨田区走り方教室#葛飾区走り方教室#足立区走り方教室#荒川区走り方教室#かけっこ