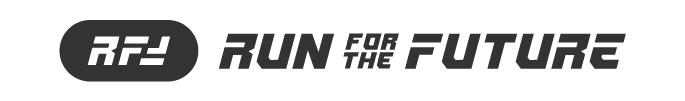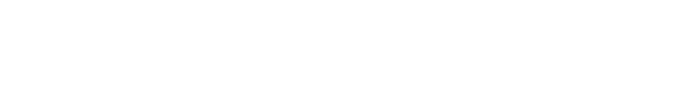みなさんこんにちは!三枝です。
久しぶりになってしまいました「はえちゃんのこころシリーズ」です!
今日は「感覚と理論」というテーマで書いてみようと思います。
先週の木曜日に、舘野コーチと三輪コーチから「自分に合った感覚」についてお話があったと思いますが、個人的にもこれについてお伝えしたいことがあります。
短距離は、一見すると「速く走る」だけのシンプルな競技に見えますが、その裏には驚くほどの奥深さがあります。
スタートの反応、腕振り、脚の運び、そしてゴールまでのスピード維持。
それぞれの動きには科学的な「理論」があり、同時に「感覚」が重要な役割を果たします。
この競技には、理論と感覚の両方が不可欠なのです。
競技者には「感覚派」と「理論派」がいます。
感覚派は体で覚え、理論派は考えて動きます。
両者とも重要で、感覚で掴んだことを理論で裏付け、理論で学んだことを感覚で実践すると、より速く走れるようになります。
自分に合った方法を大切にしつつ、両方のアプローチを少しずつ取り入れながら成長する。それは自分の体と向き合い、独自の走りを見つける終わりのない旅です。この挑戦を楽しむことで、皆さんはさらに強く、速くなることができます。これからの練習や試合に全力で挑み、この陸上競技の魅力を存分に感じてほしいなと思います。
少し長くなりますが、私自身のことについても書いてみようと思います。
ちなみに、私は「感覚派」でした。

はじめて出場した2013年ソフィアデフリンピック。
感覚派の私が現役時代にタイムを伸ばすのに効いたと考えているのは、ウエイトトレーニングとフラット接地という技術の獲得でした。これで10秒台のタイムを達成できたと考えています。
高校までは、趣味程度に陸上に取り組んでいましたが、社会人(19歳)になってから先輩のアドバイスをもらいつつも、基本は独学で本格的に競技に取り組み始めました。
私は体の動きやタイミングに敏感で、それを活かして様々なトレーニングを実験的に取り入れることで、自分にとって最適なトレーニング方法を見出すことができました。
まず、ウェイトトレーニングは、パワー系トレーニングとして筋力と瞬発力を鍛えるために行っていました。スプリントに特化した動きで言うと、クリーン&スナッチ、スクワット、デッドリフトなどの複合的なエクササイズが効果的でした。これらの運動は体幹と下半身の爆発力を向上させ、スタートダッシュと加速力に大きな効果がありました。
感覚派の私にとって最も重要だったのは、重りを使ったトレーニングの中で、最大の力を発揮するベストなタイミングを体で感じ取ることでした。
具体的には、
✓スクワットの立ち上がり
✓デッドリフトでの腰の引き上げ
✓ジャンプ系トレーニングでの反動 など
大きな重量を扱いながらも素早く動く動作において、力を入れるベストなタイミングを体で覚えることを大切にしていました。
また、私は100m走の中でも中間区間が得意でしたので、それを活かすために、加速から最大速度への移行時における力の伝達に特に注力しました。筋力向上と同時に、力をスムーズに伝達する感覚を意識的に磨いたことで、フォームや重心の位置も自然と改善されたと考えています。
他にもプライオメトリック系のトレーニングが得意だったため、その強みを活かして記録を伸ばすことができたと考えています。
当時はハイハードル(106.7㎝)を5台連続でポンポンと軽々と跳び越えていました。
・・・今は無理です(笑)
当時の身長・体重は177cm・60kgでしたが、4年後には180cm・75kgにまで成長しました。
この体格の変化は、ウエイトトレーニングによる筋肉量の増加によるものです。体重増加に伴う筋力の向上により、スプリントにおける爆発力と持久力も高まったと考えています。

高校時代の私。若いし、細い(笑)
ちなみに自己記録はクリーン110kg・スナッチ75kg・デッドリフト180kg・ハーフスクワット200kgでした。今思えば鍛えすぎだったかもしれませんね(笑)

左から2番目。ガラが悪くてすみません。体育会男子って大体こういう写真撮るんです。(笑)ウエイトトレーニングで明らかに身体が変わったことがわかるかと思います。・・・小学生のみなさんはまだウエイトトレーニングはしたらダメですよ!
次に「フラット接地」についてです。
以前はフォアフット接地(足のつま先側での接地)を重視していたことでふくらはぎに過度な力がかかり、筋肉が発達し太くなっていましたが、フラット接地を意識するようになったことで、より楽に走れるようになったのは大きな成果でした。
フォアフット先接地では、脚を必要以上に高く上げてしまったり、余分な力が入ってしまいがちでしたが、フラット接地に切り替えることでこれらの問題点が改善されました。
感覚的には、フラット接地により地面への力の伝達が効率化され、最小限のエネルギーで滑らかな加速を実現できました。フォームの安定化によってスプリントが楽になったという実感は、力が効果的に前方推進力に変換されている証だと考えています。
フォアフット接地からフラット接地へ変更したのは、コーチのアドバイスがきっかけでした。フォアフット接地の継続は、怪我のリスクが高く、また疲労が蓄積されやすく、10秒台の達成を阻害する可能性があると指摘されたのです。
また、コーチから「絶対に10秒代を出せる」という言葉をもらっていたので、それが大きなモチベーションになっていて、このコーチのアドバイスを信じて実践してみることにしました。
これは2013年のデフリンピックの4か月前の強化合宿での出来事で、今考えるとなかなか思い切った挑戦だったなと思いますが、感覚を重視するタイプの私だからこそ、走りフォームの切り替えもスムーズにできたのだと思います。

2013年デフリンピック100mの様子。 100m二次予選では10秒95(+1.0)で自己ベスト更新。日本ろうあ21世紀初の10秒台でした!
私の10秒台達成の鍵となったのは、ウエイトトレーニングとフラット接地の導入だったと確信していますし、それをただこなすだけではなくて、力の入れ方やタイミング、走りにつなげることを感覚的に意識しながら取り組んだことがよかったと思っています。
RFFのメニューには、走る以外にもいろんなことをやりますよね?
「これって走るのに役立つのかな?」って思うこともあると思いますが、自分の身体をうまく使おうと考え、頑張る練習は感覚を磨くことにつながり必ず将来役立ちますので、みなさんにはぜひ楽しみながら取り組んでもらえたらと思います!
Run for the Future では、墨田区と多摩市で定期スクールを開催中です。
それぞれ随時、体験・入会を募集しておりますので、ご興味がおありの方は、まずは体験からお気軽にお越しください。お申し込みはこちらからお願い致します。
また、公式Instagramでは、日々の練習の様子やイベントの案内を発信中です!
ぜひフォローいただき、チェックしてみてください!